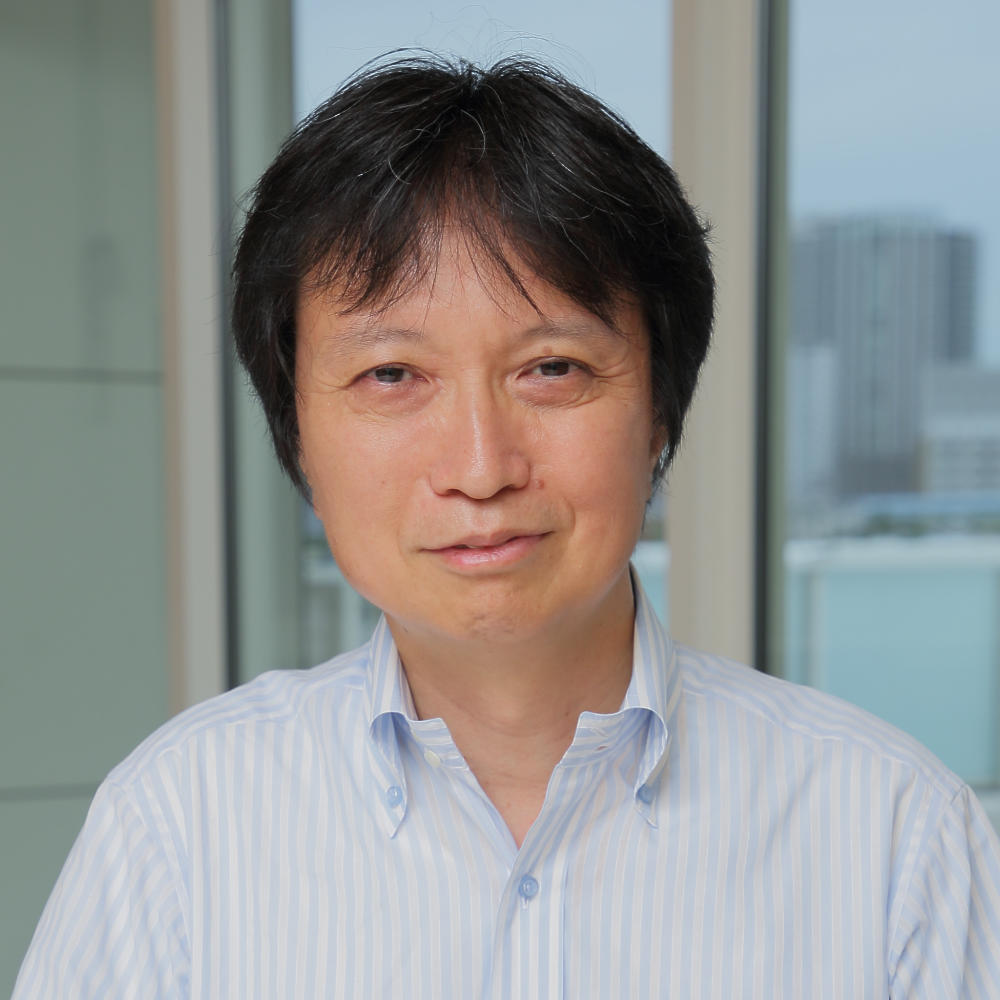本連載は、画一的な効率性を重視した「旧来型の組織」では殺されてしまう創造性を発揮するための「新しい組織」について考えます。ここでの「新しい組織」とは、旧来型の組織と完全に置き換えるのではなく、創造性が必要とされる業務を切り離して旧来型の組織とは別の考え方で運営する組織を指します。
今回取り上げるのは、日本の企業が特に好きな「競合他社事例」です。「欧米企業」という明らかな目標があり、市場全体が拡大して競合と一緒に業界全体が伸びていた時代には必須だったものが、現在はその有効性が低くなっており、ある意味で「思考停止」の典型例とも言えます。果たして「これ本当に必要?」でしょうか。
「他の人は飛び込みました」
日本企業が新しい事業を始めたり新製品を開発したり、あるいはコストダウンや効率化のための社内の何らかの取り組みを始める場合等にまず気にすることが、「競合はどうしているか?」ということです。
「沈みかけている船から乗客を海に飛び込ませるにはどうするか?」という有名な民族ジョークがあります。例えばアメリカ人には「英雄になれますよ」、イタリア人には「もてますよ」、ドイツ人には「それが規則です」、フランス人には「飛び込まないで下さい」といった具合です。
では日本人はどうすれば飛び込むかと言えば、「他の人は全員飛び込みました」だそうです。いかにも納得できる話で、良くも悪くも「周りに合わせる」のは自他ともに認める日本人の特徴のようです。
70年代までの思考回路から抜けられず
ビジネスという「戦い」において競合という「敵」を研究し、ベンチマークの対象とすることはもちろん重要ですが、問題は、自分たちの施策そのものを競合に学ぼうとする姿勢です。これが有効なのは、「圧倒的に劣位であるほうが優位な相手に追いつこうとする」場合です。例えば1970年代までの日本やいまの新興国がこの状況に該当します。
そしていま、すでに日本の社会・ビジネス環境は成熟期に入っていて、このような戦い方は適合しなくなってきています。にもかかわらず、依然として「競合他社事例」は、前述の日本人の性格とも相まって、大抵の担当者が何らかの提案をしてきたサプライヤに要求することの代表例です。
また社内で企画を通すときにも、新しいことは「できない理由」が先に出て来て先に進まないのに、「(業界リーダーの)A社はすでにやっています」と言えば簡単に承認が降りたりします。つまりマネジメントの側も、この思考回路から抜けられていないケースも多いと言えます。
「真似してしまわない」ために
斬新と思えるアイデアも、実はどこかにあったものの組み合わせでしかないとよく言われます。したがって他社事例を参考にするのは決して間違ってはいませんが、問題はその対象の業界です。アイデアを同じ業界の競合他社からもってくれば、誰でも気づくことだったり、後追いだったり、下手をすれば特許等を侵害するといった形で良いことはありませんが、それをなるべく「遠くの世界」から借りてくれば、簡単には気づかないような斬新なアイデアにすることができます。
その場合、借りてくる相手との類似性を単に「同じ製品を扱っている」とか「見た目が似ている」という視点でとらえているわけではありません。ビジネスの「肝」(リピート率を上げる、保守でも利益を上げる、稼働率を上げる、熱狂的ファンを増やす等)や、仕事関係者との関係性(顧客と直接つながる、顧客同士の紹介で売れる、顧客・物流業者・サプライヤとの力関係等)における共通点を探します。それによって、一見関係なさそうな世界からアイデアを借りてくる(人間の世界のビジネスをペットや人形に当てはめる、スマホのアプリのアイデアを自動車に適用する等)ことができます。
オリジナリティがこれまで以上に求められる時代、競合他社事例は何のためにあるのか、改めて考えてみる必要があるでしょう。「真似するため」にあるのではなく、むしろ「真似してしまわないため」にあるのではないでしょうか。
2014年2月1日更新 (次回更新予定: 2014年3月1日)
会社の「これ本当に必要?」 の更新をメールでお知らせ
下のフォームからメールアドレスをご登録ください。